年金制度の基本:いくら払って、いくらもらえるのか?
日本の公的年金制度は「二階建て構造」と呼ばれ、1階部分にあたる国民年金(基礎年金)は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入義務を負う。2階部分の厚生年金は、主に会社員や公務員が対象である。
令和7年度の国民年金保険料は月額1万7510円である。これを20歳から60歳までの40年間納めたと仮定すると、総額は約840万円になる。
一方で、65歳から年金を受給した場合、基礎年金の満額支給額は月額6万9308円、年間で約83万円。つまり、おおよそ75歳あたりで支払った保険料と受け取った年金額が同等となる。
厚生年金に加入していた場合は、年収や保険料納付額に応じて受給額が上乗せされる。たとえば、年収460万円で38年間就業した場合、本人負担の保険料はおよそ1650万円だが、年金受給額は年間約185万円となり、約9年で元が取れる計算となる。


支払額と受給額のシミュレーション事例
実際に、支払った保険料と将来的な年金受給額を比較してみよう。以下は代表的な2パターンのシミュレーションである。
国民年金のみ加入(40年間)
- 総支払額:約840万円
- 年間受給額:約83万円
- 元が取れる年齢:75歳1ヶ月
- 90歳まで生存した場合:受給総額約2000万円 → 支払額の約2.4倍
厚生年金加入(年収460万円・38年間)
- 本人負担分の総支払額:約1650万円
- 年間受給額:約185万円
- 元が取れる年齢:74歳5ヶ月
- 90歳まで生存した場合:受給総額約4625万円 → 支払額との差額:約2975万円
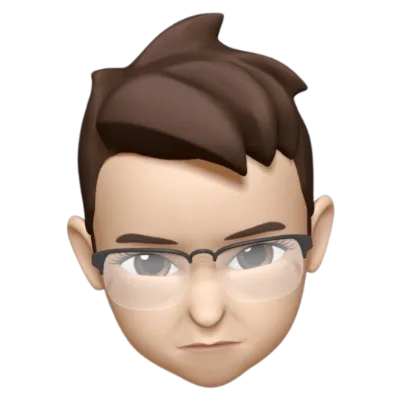
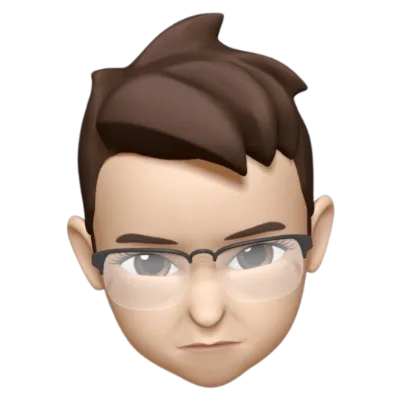
これらの試算からわかるのは、「平均寿命を超えて生きれば生きるほど、年金制度は得になる」という点である。
なぜ「年金は損」と言われるのか?
しばしば「年金は元が取れない」「損するだけだ」という声が聞かれる。その背景にはいくつかの誤解や感情的なバイアスが存在する。
まず、年金は投資や貯金とは異なる「保険制度」であるという点を理解しておく必要がある。年金制度は賦課方式、つまり現役世代の保険料によって高齢者の年金がまかなわれている仕組みであり、将来の自分の支払った分がそのまま戻ってくるわけではない。
また、「早く亡くなったら損だ」という考えも根強いが、それは年金制度を誤って投資商品として見ているからに他ならない。本質は「長生きリスク」に対する保険であり、長生きすればするほどリターンが大きくなる構造である。
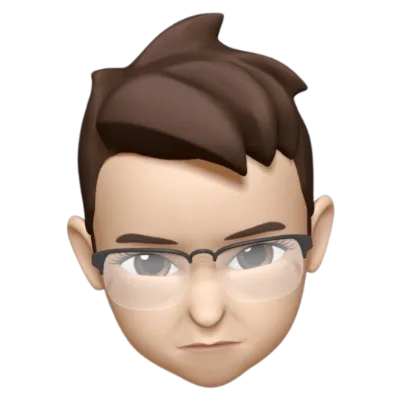
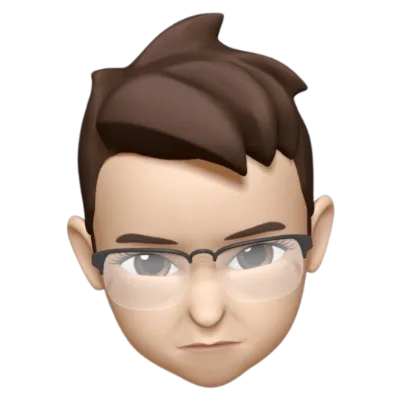
さらに、年金受給額の平均値や一部のモデルケースだけを見て「足りない」と判断するのも問題である。個人のライフスタイルや資産状況、住居費、医療費などを含めた総合的な老後設計の中で評価するべきである。
仮に元が取れないとしても意味はある?
仮に75歳以前に亡くなったとして、「支払った年金保険料より受け取る額が少なかった」という結果になった場合でも、年金制度は完全に無駄だったと切り捨てるのは早計である。
年金には老齢年金以外にも、障害年金や遺族年金といった機能が含まれている。たとえば、現役時代に病気やケガで重度の障害が残った場合、障害年金が支給される。また、加入者が死亡した場合には、配偶者や子に遺族年金が支給されるケースもある。
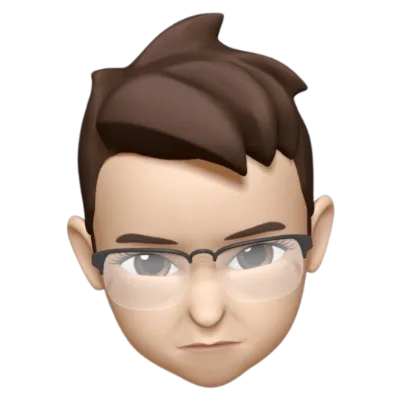
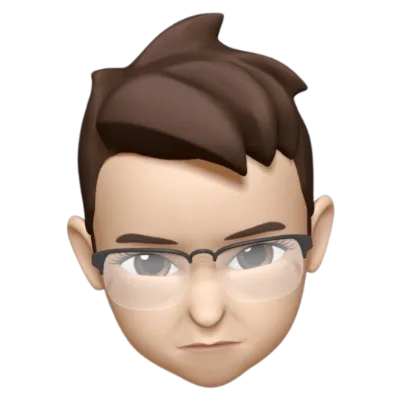
つまり、公的年金制度は「長生き保険」であると同時に、「万が一保険」としての性質も持つ。その価値は、単なる支払いと受給の損得勘定では計れない。
長寿社会における年金の存在意義
日本は世界でも有数の長寿国であり、今後も高齢化は進行する見通しである。90歳を超えるまで生きる人の割合は着実に増えており、人生100年時代も決して絵空事ではない。
このような社会では、年金の持つ「終身給付」という特徴は極めて重要である。たとえ資産を持っていても、将来のインフレや医療費の高騰など、予測不能なリスクに対応するうえで、公的年金のような安定収入は大きなセーフティーネットとなる。
さらに、年金にはインフレ対応の仕組み(マクロ経済スライド)も組み込まれており、一定程度は物価変動に応じた調整がなされる。完全な防衛策ではないにせよ、ゼロ金利の預金よりも遥かに実効的な収入源である。


まとめ
「年金は元が取れるのか?」という問いは、単なる金銭の損得を超えた問いである。
制度の仕組みを正しく理解し、人生のリスクに備えるという視点から見れば、年金はむしろ「得をする可能性が高い保険」であると言える。特に90歳を超えて生存した場合には、支払額をはるかに上回る年金を受け取ることができる。
加えて、障害年金や遺族年金といったセーフティーネット機能を含む公的年金制度は、単なる老後資金の柱というだけでなく、「人生の不確実性」に対する保険でもある。
老後の生活を安心して送るためには、年金という仕組みの本質を理解し、早いうちから計画を立てることが重要である。その第一歩として、「年金は本当に元が取れるのか?」という問いに自らの頭で向き合う姿勢が求められる。

